参加申込み
参加申込みには会員登録(無料)と
ログインが必要になります。
会員登録はこちら

大柿 顕一朗 氏
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局
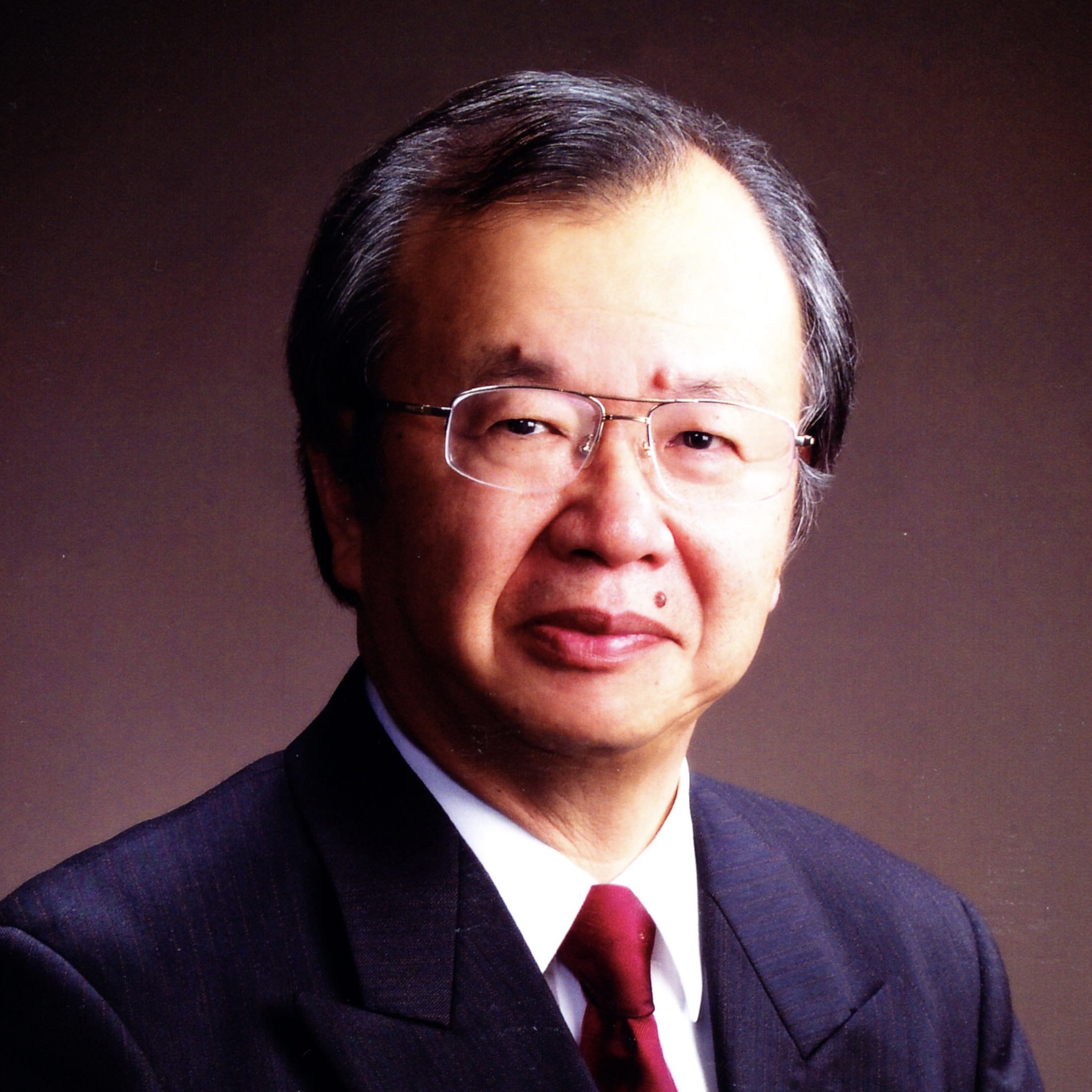
河田 惠昭 氏
関西大学 社会安全学部

平田 直 氏
一般社団法人防災教育普及協会
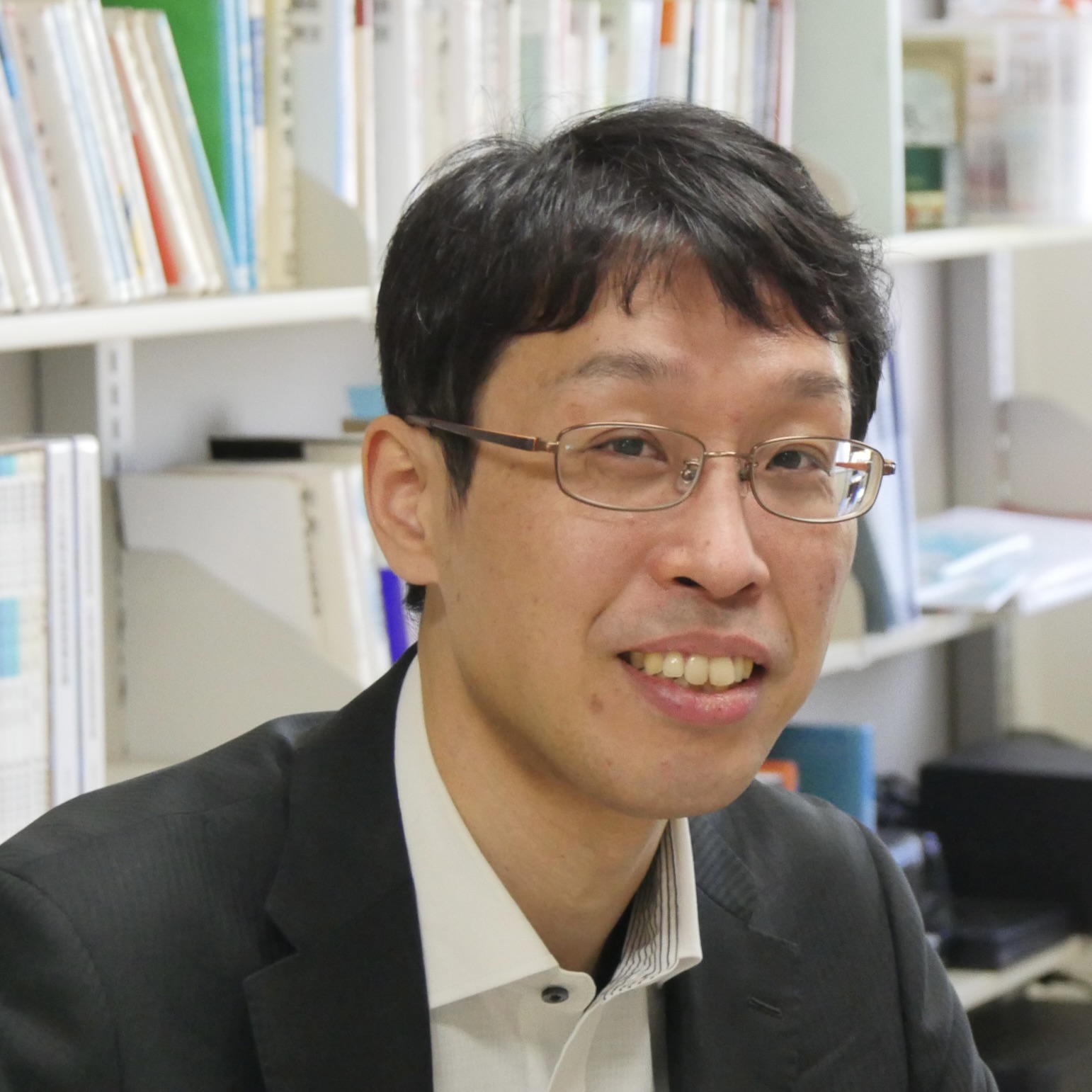
後藤 浩之 氏
京都大学 防災研究所

岸本 隆久 氏/吉沢 昌兵 氏
一般社団法人まるごと防災協議会

伊勢 正 氏
防災科学技術研究所 先進防災技術研究連携センター

大和田 泰伯 氏
国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所

塚越 秀行 氏
東京科学大学 工学院システム制御系
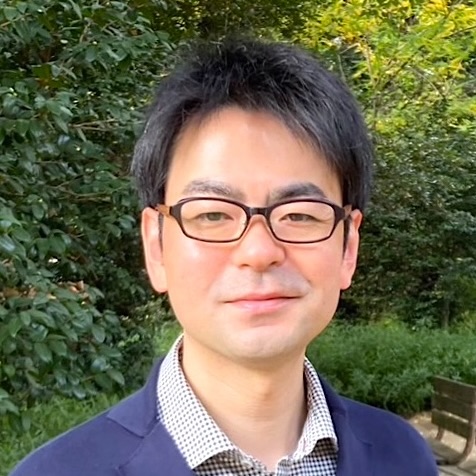
小田 隆史 氏
東京大学 総合文化研究科

吉田 克也 氏
一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会

防災・減災オンラインセミナー2025
2025年9月1日(月)〜2025年9月30日(火)
※最終日は17:00まで
防災ログ特設サイト
無料(事前登録制)
防災ログ実行委員会
特定非営法人都市防災研究会
6.5単位(JSCE25-0896)
ホーム画面右上から会員登録(無料)を行い、
自動返信メールで届くパスワードを使用してログインを行います。
会員登録済みの方
・会員情報でログインしてください。再登録は不要です。
・パスワードはホーム画面右上の「ログイン」から再発行できます。
・パスワードが届かない場合は事務局までご連絡ください。
本ページの「セミナー申込み」ボタンをクリックし、
全項目入力後「お申し込みをする」をクリックすると登録完了です。
本ページの「オンラインセミナー動画」ボタンから講演動画ページにお進みいただけます。 「会員登録(無料)」、「ログイン」、「参加申込み」が必須になります。
【確認事項】
・動画の録画、録音等、及び資料の二次利用、SNS投稿は禁止とさせていただきます。
・セキュリティ等の関係でご動画を視聴できない可能性がございます。
その場合は別のパソコンやスマートフォンでご覧ください。
防災・減災オンラインセミナー2025は、公益社団法人土木学会 継続教育(CPD)のガイドラインに基づき認定されたプログラムです。
| 申請期間 | 2025年9月1日(月)〜2025年9月30日(火) ※17:00まで |
|---|---|
| 認定番号 | JSCE25-0896 |
| 認定単位 | 6.5単位 |
| 申請条件 (必須) |
CPD受講証明書の発行には下記4点を満たしている必要があります。
1)本特設サイトからセミナーを申し込み、全てのセミナー受講を行うこと。 ※防災ログの会員登録情報が最新情報になっているかご確認の上、申請してください。 |
1. 申請条件4点(必須)をご確認いただき、2025年9月30日17:00までに下記資料2点を事務局にご提出ください。
①受講証明書(ダウンロードはこちら)
・ファイル名を「社名_名前」に変更し、Wordデータでご提出ください。
②受講して得られた所見(ダウンロードはこちら)
・ファイル名を「社名_名前」に変更し、Excelデータでご提出ください。
2. 申請条件を満たしていることが確認できましたら、受講証明書に押印の上、メールにて送付します。
1. 2025年10月1日以降は動画視聴とCPD申請はできませんので、視聴漏れにはご注意ください。
2. 土木学会以外の団体に提出する場合の方法等は提出先団体に事前にご確認ください。
3. 他団体が運営するCPD制度に関する内容については回答いたしかねます。
参加申込み(左の赤ボタン)後、
講演動画を視聴できます。
9月1日(月)から視聴可能

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
内閣府 宇宙開発戦略推進事務局 準天頂衛星システム戦略室 参事官補佐
大柿 顕一朗 氏
1997年4月 運輸省(現国土交通省)入省。
以来、管制情報処理システムや無線電話・航法装置をはじめとした航空保安無線施設などの運用と維持管理業務に従事。
2023年4月 国土交通省大臣官房運輸安全監理官付運輸安全調査官
2025年4月より現職
大規模災害発生時の早期緊急警報等の配信は、早期避難や被害拡大の防止に不可欠であり、多様な通信手段の確保等、災害時における通信の維持が重要である。本講演では、衛星システムの活用により、山間部などの通信網の脆弱な地域や地上インフラの被災により通信が途絶した状況においても災害情報等を配信できる、宇宙インフラ「準天頂衛星システム(みちびき)」が提供する防災機能「災害危機管理通報サービス」について説明する。
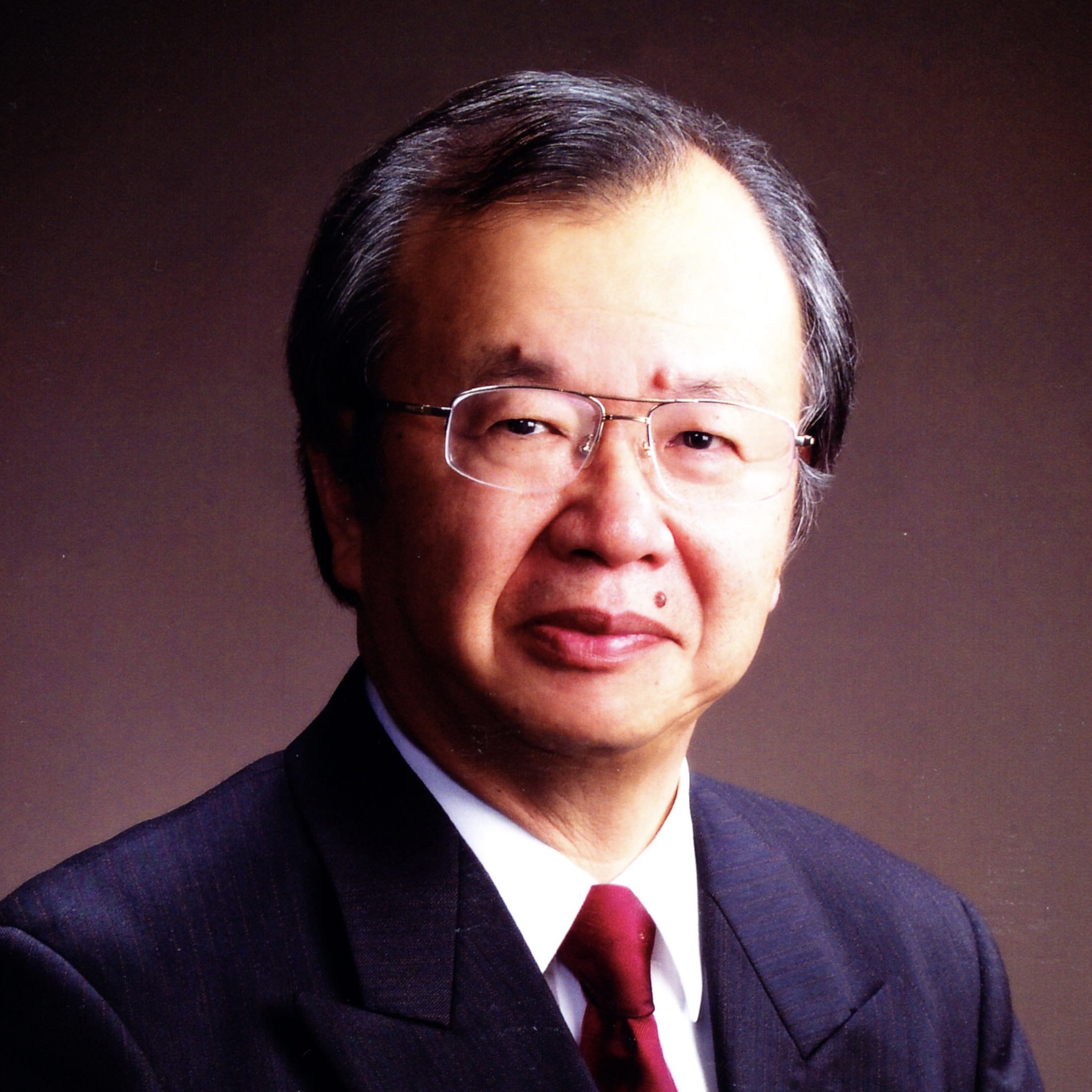
2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
関西大学 社会安全学部 特別任命教授・社会安全研究センター長
河田 惠昭 氏
関西大学特別任命教授・社会安全研究センター長、人と防災未来センター長。京都大学名誉教授。国連SASAKAWA防災賞、防災功労者内閣総理大臣表彰など受賞多数。24年日本自然災害学会功績賞、瑞宝中綬章受章。日本自然災害学会および日本災害情報学会の会長を歴任。著書に『これからの防災・減災がわかる本』『にげましょう』『津波災害(増補版)』『河田惠昭自叙伝』等
平成8年度に新設予定の防災庁では、本気の事前防災を実現するために『社会現象の相転移』を活用することになっている。東京都の都心南部直下地震による最大死者数は、区部で約5700人と推定している。仮に地震時に相転移が発生すれば、死者数はその25倍の約14万2500人に増加する。その原因を事前に明らかにし、対策すればよい。従来の総花的な対策では実行不可能だ。

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
一般社団法人 防災教育普及協会 会長
平田 直 氏
一般社団法人防災教育普及協会 会長
東京大学名誉教授
東京大学理学部地球物理学科、同大大学院修士・博士課程を経て、同大理学博士。東京大学理学部助手、千葉大学助教授、東京大学地震研究所助教授、同教授、同研究所長、同所地震予知研究センター長を務める。同大学在職中・在職後に国立研究開発法人 防災科学技術研究所 参与(兼)首都圏レジリエンス研究推進センター長(2022年3月まで)。
政府の地震調査委員会委員長
気象庁 地震防災対策強化地域判定会会長
南海トラフ地震に関する評価検討会会長
内閣府 中央防災会議専門委員など、国の地震防災行政でも要職を歴任する。
平成27年度 防災功労者防災担当大臣表彰 受賞
平成29年度 防災功労者内閣総理大臣表彰 受賞
「地震を知って 震災に備える」 (亜紀書房:2024,08月)
「首都直下地震」(岩波書店)ほか著書多数。
2025年3月に、南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定が公表され、これを受けて、国は、南海トラフ地震防災対策推進基本計画を策定した。約10年ぶりの被害想定と対策計画の概要と、私たちが注意すべき防災対策について議論する。
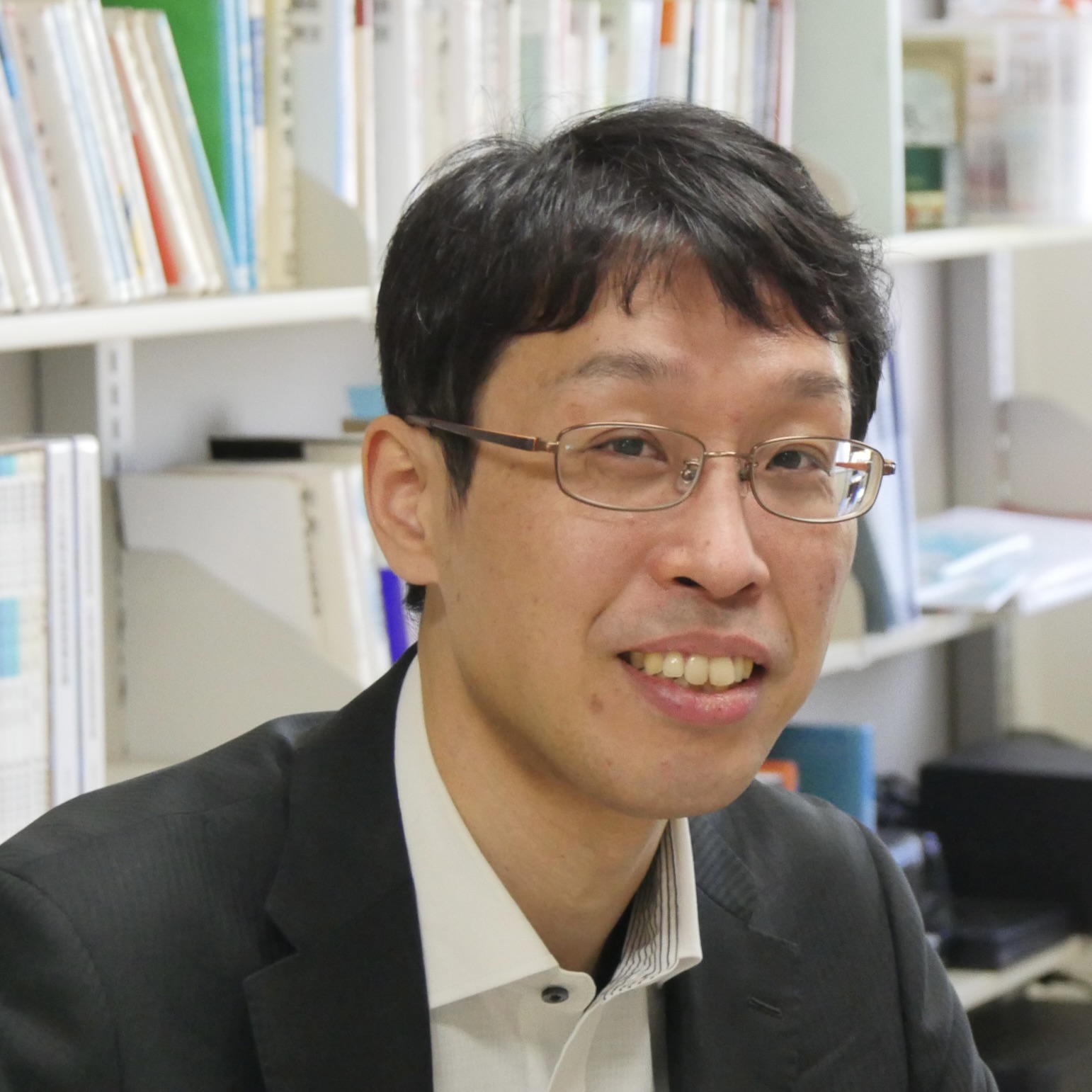
2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
京都大学 防災研究所 教授
後藤 浩之 氏
2003年京都大学工学部卒,2005年京都大学工学研究科修了,2006年京都大学工学研究科博士学位取得.2007年京都大学防災研究所助教,2015年同准教授を経て,2023年より現職.土木工学を背景とした地震工学,地震学,地盤工学を専門とする.地震災害における基礎的な学術研究を行うとともに,地震災害の軽減に向けた次世代技術の開発研究を進めている.2025年日本地震工学会第1回大崎順彦賞受賞.
2024年能登半島地震では道路・水道をはじめとするインフラ施設の被災が,被災地の応急対応や復旧に多大な影響を与えた.人口減少を迎える現代社会では,このような災害が各地で予想されることから,人的リソースに頼り切らない新たな都市機能マネジメント手法が求められている.能登半島地震をはじめとする近年の地震災害を踏まえ,都市機能を低減させにくくするための新たなインフラ減災技術について最新の動向を紹介する.

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
一般社団法人まるごと防災協議会 代表理事/幹事
岸本 隆久 氏/吉沢 昌兵 氏
①一般社団法人まるごと防災協議会代表理事
①一般社団法人防災事業経済協議会理事
①防災士・ひょうご防災リーダー
①帝人フロンティア(株)新事業開発室主管
②日本セイフティー(株)ラップポン事業部主任
「まるごと防災」のビジョンは「事業継続」と「復旧復興」の貢献です。
南海トラフや直下型地震に加え、地球温暖化の影響による台風の激甚化頻発化も危険視されており、未曾有の複合型の災害にも備えなければなりません。その解決策として本日は、事前の被害軽減対策として室内の「安全対策」と「火災対策」、そして避難生活の質の向上を目指した「備蓄対策」を提案します。備蓄対策についてはラップポンで災害関連死削減を目指しています。

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
防災科学技術研究所 先進防災技術研究連携センター 研究統括
伊勢 正 氏
コンサルティング会社を経て、2013年4月より現職(防災科研)。主に、災害時における情報共有・利活用システムの研究開発、災害情報の標準化等に従事。2023年10月より、先進防災技術連携センター・研究統括。戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期の研究開発責任者。
災害時の情報共有。都道府県の情報システムに市町村が情報入力するという体制が一般的である。しかし、被災している自治体が情報入力という枠組みには、激甚災害になればなるほど情報発信を期待できないという決定的問題がある。熊本地震、能登半島地震・・・国の研究機関として、緊急支援に携わった登壇者が、現状の問題とあるべき姿を解説する。

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
国立研究開発法人情報通信研究機構 ネットワーク研究所 レジリエントICT研究センター サステナブルICTシステム研究室 主任研究員
大和田 泰伯 氏
アドホックに構築・運用できる自律分散型の情報通信システムの研究開発に従事。博士(工学)。学位取得後、2007年から新潟大学災害復興科学センター特任助教、2008年に株式会社スペースタイムエンジニアリング設立、代表取締役社長。2010年より国立研究開発法人情報通信研究機構にて現職。
南海トラフ地震では、広域かつ長期に及び停電・通信途絶が発生するとの予測が示されている。そのような状況下においても業務継続が必要な自治体や指定公共機関などは、これらの状況を想定したシステム設計が重要である。本講演では、そのような状況下でも使い続けられる情報通信システムの研究や実装事例について紹介する。

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
東京科学大学 工学院システム制御系 教授
塚越 秀行 氏
略歴:1992年 東京工業大学 工学部制御工学科 卒
1994年 同大学院 修士課程制御工学専攻 修了
1998年 同大学院 博士課程機械物理専攻 修了 (博士(工学)取得)
1998-1999年 日本学術振興会特別研究員PD(東京工業大学)
1999-2004年 東京工業大学工学部助手
2001-2004年 科学技術振興機構さきがけ21研究員兼任
2004-2021年 東京工業大学大学院理工学研究科助教授
(その間、改組により同大工学院システム制御系准教授)
2021年- 東京工業大学工学院システム制御系教授
流体には、変幻自在性・高出力密度・柔剛可変特性など、電気では生み出しにくい特性が秘められています。これらの特性をロボット設計に適切に取り入れることで、従来技術では対応困難だった環境にロボットを導入できる可能性が開けます。本講演では、講演者の研究室でこれまでに開発してきた、様々なタイプの流体レスキューロボットを動画を交えながら紹介します。そして、それらの災害時と平常時の運用法について展望します。
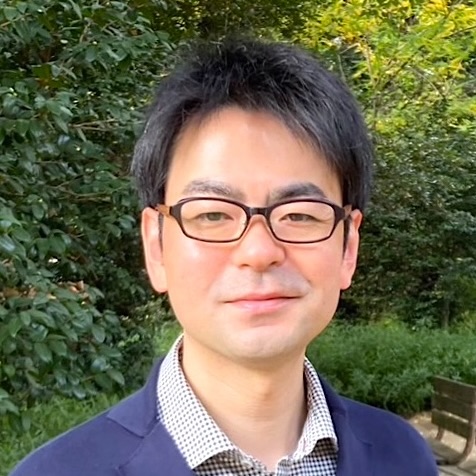
2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
東京大学 総合文化研究科 准教授
小田 隆史 氏
専門は地理学。外務省専門調査員、カリフォルニア大学バークレー校フルブライト研究員、お茶の水女子大学シミュレーション科学教育研究センター助教、宮城教育大学防災教育研修機構准教授・副機構長などを経て現職。現在、日本安全教育学会理事、防災科学技術研究所客員研究員、東北大学災害科学国際研究所特任准教授(客員)。編著に『教師のための防災学習帳』(朝倉書店)、監著に『学校安全ポケット必携』(東京法令出版)。
近年、全国各地の災害の危険性を把握し、地域特性に応じた防災対策を検討するための多様な地理情報が、ウェブ上で公開・提供されるようになっています。特に、ハザードマップや地形、土地利用などの地理情報は、学校教育や自主防災活動、行政の備えにも有効です。本講座では、こうした情報をウェブ上でどのように入手し、どう活用できるかについて、地理学の視点から解説し、地域に根ざした実践的な防災地理情報の活用法を学びます。

2025年9月1日(月) ~ 2025年9月30日(火)
一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会 理事室 常務理事
吉田 克也 氏
2021年11月5日 東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター【DMTC】を支援するために、東京大学関連公益法人等に該当する一般社団法人災害対策トレーニングセンター支援会【DMTC-SA】を設立し同日常務理事に就任。教育カリキュラムの開発・実施・運営・営業に従事。一般財団法人生涯学習開発財団認定ワークショップデザイナーマスター(通称認定WSDマスター)
東京大学生産技術研究所附属災害対策トレーニングセンター【DMTC】が実施している災害対策人材育成プログラムの修了生を中心に数多くの災害対策士を認定し、様々な組織体のレジリエンス力を高める活動を紹介します。
参加申込み(左の赤ボタン)後、
講演動画を視聴できます。
9月1日(月)から視聴可能試聴可能