参加申込み
参加申込みには会員登録(無料)と
ログインが必要になります。
会員登録はこちら
2025年1月3日(月)〜3月31日(月)に開催された「World Bosai Forum Online 2025」一部プログラムの再配信になります。

岡田 恵子 氏
内閣府 男女共同参画

三本木 大士 氏
防衛省・陸上自衛隊 東北方面総監部 防衛部防衛課

玉川 修一 氏
宮城県 復興・危機管理部 防災推進課

猪狩 祐介 氏
福島県 危機管理部災害対策課

加茂 祐一 氏
仙台管区気象台 気象防災部 予報課

小野 裕一 氏
一般財団法人世界防災フォーラム

福島 洋 氏
東北大学 災害科学国際研究所

川内 淳史 氏
東北大学災害科学国際研究所 災害人文社会研究部門 歴史文化遺産保全学分野

林 春男 氏
京都大学/Iーレジリエンス株式会社
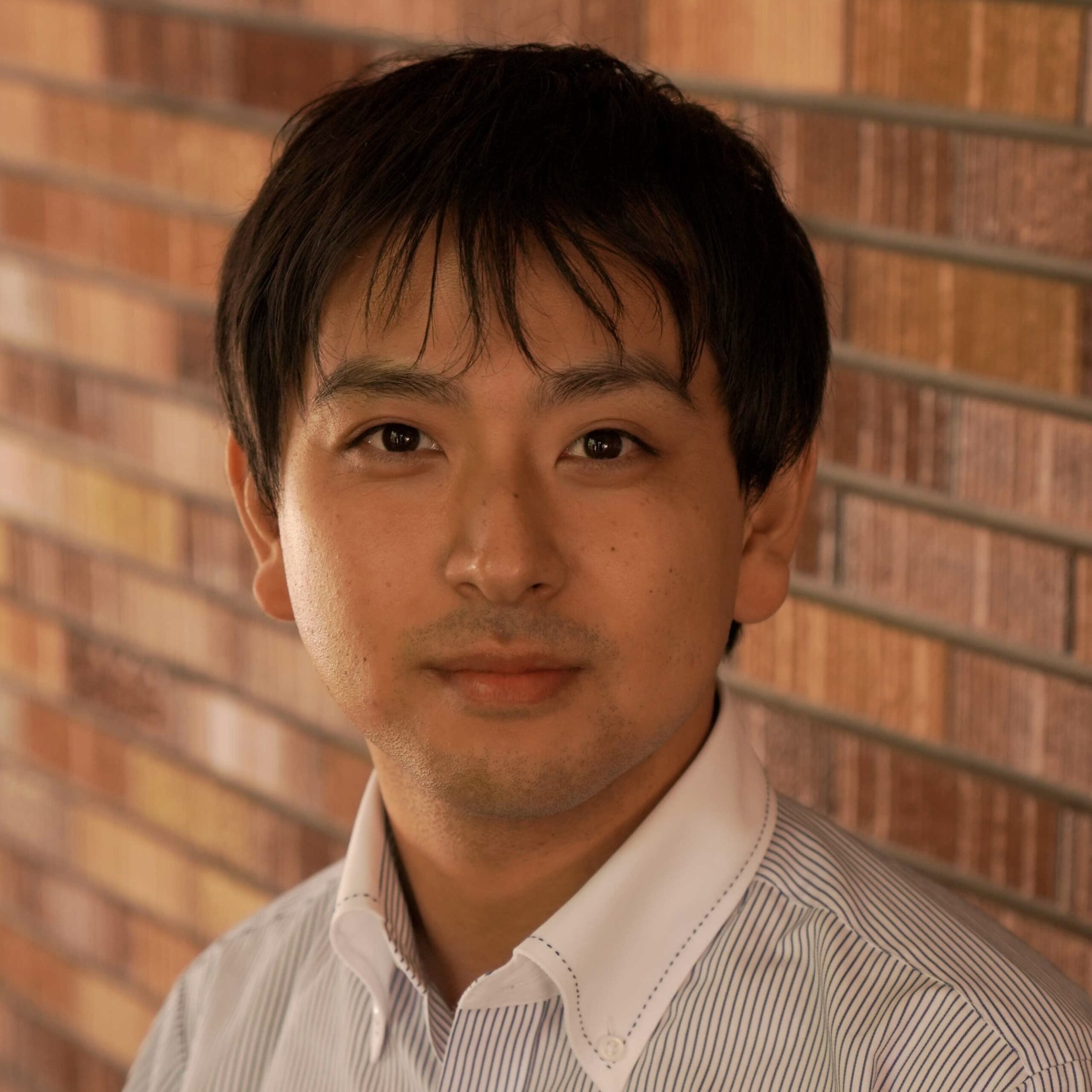
田中 智大 氏
京都大学 防災研究所

河田 惠昭 氏
関西大学 社会安全学部

南 貴久 氏
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究部

餅原 秀希 氏
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究部

新谷 絢子 氏
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 国内事業部(空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”)

World Bosai Forum Online 2025 -CPD Program-
CPD認定プログラム

World Bosai Forum Online 2025
-CPD Program-
2025年7月22日(火)〜2026年3月31日(火)
※最終日は17:00まで
World Bosai Forum Online特設サイト
無料(事前登録制)
一般財団法人世界防災フォーラム
株式会社防災ログ
8.5単位(JSCE25-0803)
ホーム画面右上から会員登録(無料)を行い、自動返信メールで届くパスワードを使用してログインを行います。
会員登録済みの方
・会員情報でログインしてください。再登録は不要です。
・パスワードはホーム画面右上の「ログイン」から再発行できます。
・パスワードが届かない場合は事務局までご連絡ください。
本ページの「セミナー申込み」ボタンをクリックし、全項目入力後「お申し込みをする」をクリックすると登録完了です。
本ページの「オンラインセミナー動画」ボタンから講演動画ページにお進みいただけます。 「会員登録(無料)」、「ログイン」、「参加申込み」が必須になります。
【確認事項】
・動画の録画、録音等、及び資料の二次利用、SNS投稿は禁止とさせていただきます。
・セキュリティ等の関係でご動画を視聴できない可能性がございます。
その場合は別のパソコンやスマートフォンでご覧ください。
World Bosai Forum Online 2025 -CPD Program-は、公益社団法人土木学会 継続教育(CPD)のガイドラインに基づき認定されたプログラムです。
| 申請期間 | 2025年7月22日(火)~2026年3月31日(火)※17:00まで |
|---|---|
| 認定番号 | JSCE25-0803 |
| 認定単位 | 8.5単位 |
| 申請条件 | CPD受講証明書の発行には下記4点を満たしている必要があります。
1)本特設サイトからセミナーを申し込み、全てのセミナー受講を行うこと。 ※防災ログの会員登録情報が最新情報になっているかご確認の上、申請してください。 |
1. 申請条件4点(必須)をご確認いただき、2026年3月31日17:00までに下記資料2点を事務局にご提出ください。
①受講証明書(ダウンロード)
・ファイル名を「社名_名前」に変更し、Wordデータでご提出ください。
②受講して得られた所見(ダウンロード)
・ファイル名を「社名_名前」に変更し、Excelデータでご提出ください。
2. 視聴履歴を確認した後、受講証明書に押印しメールで送付します。
1. 2026年4月1日以降は動画視聴とCPD申請はできませんので、視聴漏れにはご注意ください。
2. 土木学会以外の団体に提出する場合の方法等は提出先団体に事前にご確認ください。
3. 他団体が運営するCPD制度に関する内容については回答いたしかねます。
参加申込み(左の赤ボタン)後、
World Bosai Forum Onlineの動画を視聴できます。
CPD申請条件をご確認の上お進みください。
World Bosai Forum Online 2025運営事務局(株式会社防災ログ内)
東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
内閣府 男女共同参画局 男女共同参画局長
岡田 恵子 氏
1990年 京都大学経済学部卒業、同年経済企画庁入庁。
横浜市経済局、(財)連合総合生活開発研究所、法政大学大学院、内閣府政府広報室等勤務を経て、2012年 内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(経済見通し担当)
2014年 消費者庁消費者調査課長
2015年 同庁消費者教育・地方協力課長
2016年 内閣府男女共同参画局総務課長
2018年 同府経済社会総合研究所総務部長
2019年 同研究所総括政策研究官
2020年 外務省大臣官房審議官(国際協力局、経済局担当)
2022年 内閣府男女共同参画局長
人口の半分は女性であり、女性と男性が災害から受ける影響やニーズの違いに対応するには、女性が防災の意思決定や現場に参画し、男女共同参画の視点に立った災害対応が行われることが重要です。本講演では、令和6年1月の能登半島地震における男女局の取組や、防災に女性が参画するための具体的なポイントを「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン」を踏まえて説明するとともに、最近の国の動きについて紹介します。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
防衛省・陸上自衛隊 東北方面総監部 防衛部防衛課 防衛課長
三本木 大士 氏
第39普通科連隊中隊長(弘前)、陸上幕僚監部(市ヶ谷)等において勤務
ゴラン高原派遣輸送隊及び南スーダン派遣施設隊の国際任務や各種災害派遣に従事
令和6年11月15日から11月24日の間に東北管内の各地方自治体、関係機関及び陸海空自衛隊が連携して実施した大規模防災実動演習「みちのくALERT2024」を紹介し、自然災害に備えた連携強化に係る取組を情報発信。映像は、宮城県で実施した指揮所訓練及び孤立地域における災害応急救援活動等を紹介し、災害時の被害等情報の共有や関係機関との連携の必要性を説明

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
宮城県 復興・危機管理部 防災推進課 課長補佐
玉川 修一 氏
宮城県気仙沼市出身、平成11年宮城県入庁
防災推進課では地震・津波等に関する防災対策その他を担当。令和6年能登半島地震では石川県能登町への継続的な職員派遣に係る宿泊・交通などの調整を担当したほか、自身も災害対策現地情報連絡員(リエゾン)として現地での業務に従事。
宮城県はこれまで、東日本大震災をはじめ数多くの地震・津波被害に見舞われてきました。
それらを踏まえ、宮城県では今後発生が想定される地震・津波を対象として最新の地震被害想定調査を実施しました。本講演ではその内容と、地震・津波被害を軽減させるため、皆さんに日頃から備えていただきたいことについて説明します。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
福島県 危機管理部災害対策課 副課長兼主任主査
猪狩 祐介 氏
1999年4月 福島県庁入庁
2022年4月~ 現職
福島県で行っている防災への取組について「自助」「共助」「公助」ごとに講演
「自助」:マイ避難講習会、防災出前講座、自主防災組織リーダー研修会
「共助」:地域防災サポーター制度、地区防災計画策定支援
「公助」:福島県防災ポータル、福島県防災アプリ、災害ケースマネジメント 防災訓練 等

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
仙台管区気象台 気象防災部 予報課 主任予報官
加茂 祐一 氏
宮城県出身
平成25年4月~平成30年3月 仙台管区気象台気象防災部予報課調査係長
平成30年4月~令和5年3月 福島地方気象台予報官
令和5年4月~ 現職
生活に身近な天気予報、どんなデータをどのように使って作成されているかを解説します。
また、近年多発している大雨災害から身を守るための知識、天気図の読み方や防災情報に利活用についても解説します。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
一般財団法人世界防災フォーラム 代表理事
小野 裕一 氏
地理学博士。専門は気候学、国際防災政策。世界気象機関(WMO・ジュネーブ)、国連国際防災戦略(UNISDR・ジュネーブ・ボン)、国連アジア太平洋経済社会理事会(ESCAP・バンコク)で国際防災政策立案に従事。2012年に東北大学災害科学国際研究所の教授に就任。災害統計グローバルセンター長を兼務。第1回 World Bosai Forumの事務局長を務め、2018年に一般財団法人「世界防災フォーラム」を設立し代表理事に就任。
第3回国連防災世界会議の成果文書として採択された「仙台防災枠組2015-2030」では、4つの優先行動とと7つのターゲットが合意されました。これまで防災の大切さは幾多の会議で語られてきましたが、具体的な目標が示されたのは初めてです。ここまでの道のりと、防災におけるデータとエビデンスの大切さ、そして世界の防災関係者が仙台に集う「世界防災フォーラム2025」のご紹介についてお話します。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
東北大学 災害科学国際研究所 准教授
福島 洋 氏
2000年、東北大学大学院理学研究科地球物理学専攻にて修士号取得。包括的核実験禁止条約機構(オーストリア・ウィーン)に勤務後、フランスのパスカル大学(現クレルモン・オーベルニュ大学)に留学、2005年12月に博士号(火山学)を取得。京都大学防災研究所助教、スタンフォード大学訪問研究員、東北大学研究推進本部URAセンター主任リサーチ・アドミニストレータを経て2016年9月より現職。専門は測地学、地震学、火山学、防災コミュニケーション学。
防災では、自助、共助、公助のすべてが大事であるが、とりわけ重要なのが自助である。日本では、防災の重要性は広く認知されているが、長年にわたる行政を中心とした啓発や防災対策支援の取り組みにもかかわらず、個人の防災意識や対策が十分ではない状態が続いている。この状況を打破するためには、禁煙や減塩などで人々の行動変容を達成してきた保健分野の手法から学んだり、ウェルビーイングの実現という共通目標に向けた防災と保健を融合させた取り組みが有用である。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
東北大学災害科学国際研究所 災害人文社会研究部門 歴史文化遺産保全学分野 准教授 博士(歴史学)
川内 淳史 氏
東北地方を中心とした日本近現代史について研究しています。特に人びとの「生存」に関わる諸問題について地域社会史、医療・福祉史から検討しています。また歴史資料や災害資料の保存・活用についても研究しています。
東日本大震災の際には多くの国々から日本は支援を受けました。その100年前の関東大震災の際にも海外から多大な援助があったことをみなさんご存知でしょうか?このセッションでは100年前のトモダチ作戦に焦点を当て、アメリカが支援に踏み切った経緯や背景などを解説します。さらに日本人学生のお礼の手紙が740通あまりも現存していた新事実から、手紙が物語る当時の日米関係、学生の気持ち、防災に本当に大切なことは何か、などを読み解きやさしく解説します。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
京都大学/Iーレジリエンス株式会社 名誉教授/顧問
林 春男 氏
1951年東京都生まれ
1983年カリフォルニア大学ロスアンジェルス校Ph.D.(専門は社会心理学、危機管理)
2013年9月防災功労者内閣総理大臣表彰受賞
2015年〜2023年 国立研究開発法人防災科学技術研究所 所長
自然災害を含むあらゆる「困難」に対処、適応し、より豊かな生活(=レジリエントライフ)を目指す上で具体的にどのような取組が有効なのか?また何を意識して生活していくことが必要なのか?を実例を交えて解説していきます。
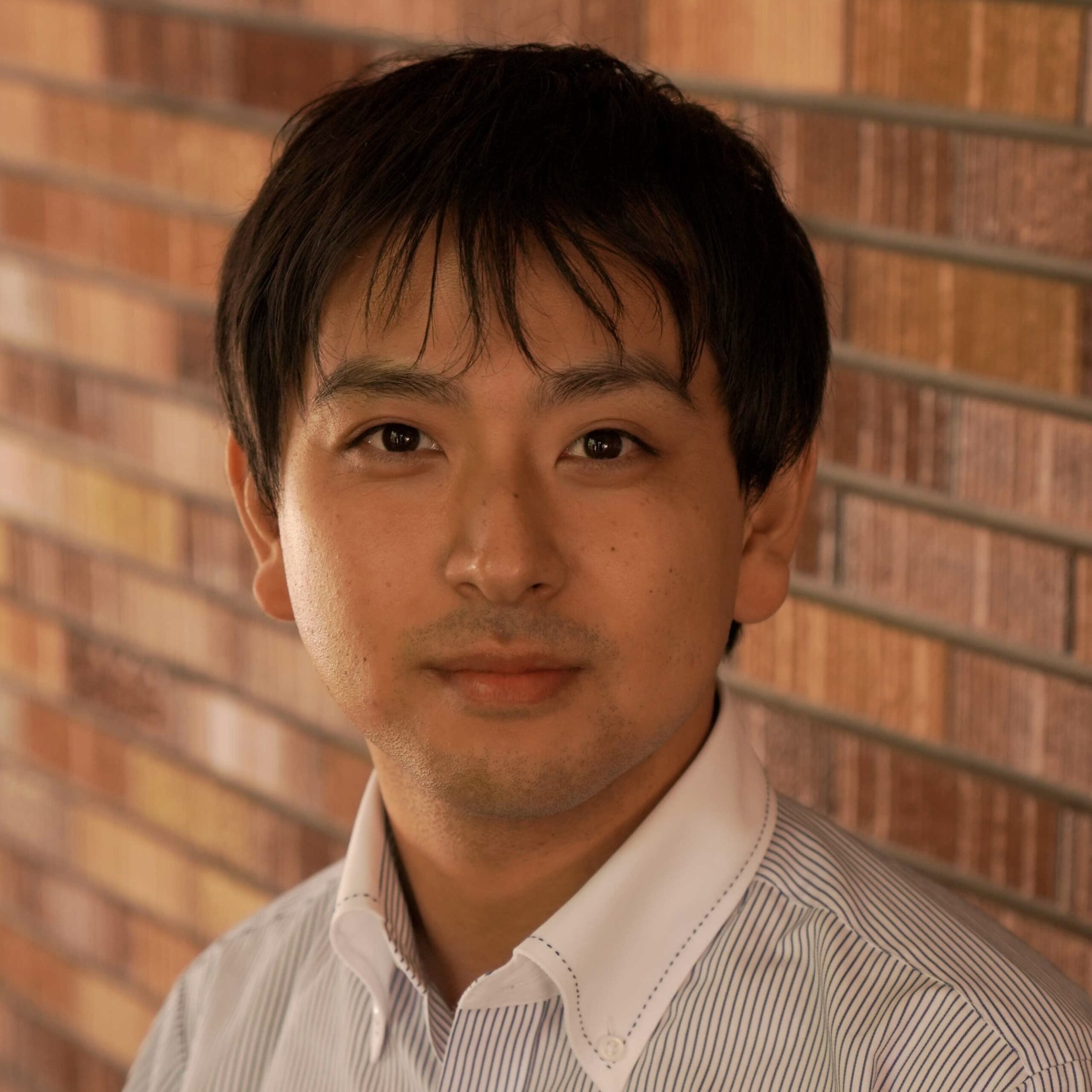
2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
京都大学 防災研究所 准教授
田中 智大 氏
2016年に京都大学で博士(工学)を取得後、2017年3月より京都大学大学院地球環境学堂、2021年4月より同工学研究科で助教.2024年5月より現職.
気候変動によって様々な風水害リスクの増大が予測されており、その把握と対策が叫ばれています。本講演は河川からの氾濫による洪水災害に着目し、その気候変動によるリスクの変化を推定するための最新研究について紹介するとともに、今後重要となる対策についてお話しします。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
関西大学 社会安全学部 特別任命教授・社会安全研究センター長
河田 惠昭 氏
関西大学社会安全学部特別任命教授(チェアプロフェッサー)・社会安全研究センター長。
工学博士。専門は防災・減災・縮災。現在、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター長(兼務)のほか、京大防災研究所長を歴任。京都大学名誉教授。2007年国連SASAKAWA防災賞、09年防災功労者内閣総理大臣表彰、10年兵庫県社会賞、14年兵庫県功労者表彰、16年土木学会功績賞、17年アカデミア賞、18年神戸新聞平和賞、22年河川功労者表彰、23年海岸功労者表彰、24年日本自然災害学会功績賞。日本自然災害学会および日本災害情報学会会長を歴任。
令和6年度日本自然災害学会賞を受賞した「相転移」を活用した事前対策を実施すれば、国難災害などの巨大災害の被害を激減できる。これは、たとえば地球規模での気候変動に伴う大都市での洪水災害にも適用でき、グローバル・スタンダードな画期的な手法であると断言できる。この相転移の発見の経緯を具体的に示し、今後の世界各国への適用の試案を紹介する。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究部 研究員
南 貴久 氏
2015年 東京大学工学部都市工学科 卒業
東京都葛飾区を拠点とするNPO法人のアドバイザーとして
防災まちづくりに携わる
2017年 東京大学工学系研究科都市工学専攻 修士課程修了 修士(工学)
2022年 東京大学工学系研究科都市工学専攻 博士後期課程 単位取得満期退学
東京大学生産技術研究所 修士研究員
2023年 埼玉県立大学 非常勤講師
2024年4月より現職
阪神・淡路大震災から30年の節目を契機に、この30年間の「災害復興とまちづくり」に関する取組みや制度等の変遷について概観する。さらに、阪神・淡路大震災をはじめとする過去の災害において実践された復興事業が、その後の地域社会にどのような影響をもたらしたかを振り返る。そのうえで、未来に積み残された課題について改めて整理を行い、少子高齢化・人口減少社会を前提とした今後の災害復興のあり方について考える。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター 研究部 研究員
餅原 秀希 氏
障害者支援や芸術活動を専門とで、現在は阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センターの研究員を務めています。日本大学芸術学部文芸学科を卒業後、慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科で公衆衛生学の修士課程を修了し、その後九州大学大学院芸術工学府で博士後期課程に進学し、芸術工学を研究しました。研究テーマは、障害者が参加する芸術活動やワークショップデザインを通じた社会福祉の向上で、これらの分野での専門性を国内外の学会や論文を通じて発信しています。職歴では、株式会社Litalicoジュニアや九州障害者アートサポートセンター、愛媛大学教育学部などで指導員や研究員として活動し、NPO法人や地域社会とも連携しながら、障害者の自己表現や社会参画を促進するプロジェクトを手掛けてきました。また、障害者芸術活動の効果に関する研究や、ワークショップのデザインと実施方法の改善に注力し、関連分野の学会にも積極的に参加しています。特に、発達障害者の芸術分野における就労支援や国際的な障害者芸術ワークショップの効果分析において実績があり、研究成果を社会に還元するための実践活動を継続しています。
「令和6年能登半島地震の被災者に対する芸術活動ワークショップの効果に関する研究」は、地震被災者が芸術活動に参加することで心理的回復やコミュニティ再生にどのような効果があるかを明らかにすることを目的としています。ワークショップを通じて被災者の感情表現やストレス軽減への影響を評価し、芸術が災害後の精神的ケアや社会的つながりを強化する可能性を探ります。研究成果は、今後の被災地支援プログラムの改善に役立てられることが期待されます。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン 国内事業部(空飛ぶ捜索医療団”ARROWS”) 看護師
新谷 絢子 氏
日本医科大学千葉北総病院、聖路加国際病院勤務。東日本大震災、熊本地震、九州豪雨等の災害支援経験し、地域医療福祉の重要性感じ訪問看護に転身。地域医療・障害福祉に従事し高齢者・障害児・者に携わる。又、東日本大震災を契機に災害時の情報の在り方に疑問を抱き、障害福祉の理解を目的に手話通訳者の資格取得し活動。「地域医療福祉×災害医療福祉」貢献を目的に2021年現職転身。医療のみならず災害弱者、福祉、地域生活の視点を重要視している
災害により平時から潜在化している地域の社会問題が顕在化する。災害弱者となる人々のニーズは幅広く、特性も多種多様で支援も多岐にわたる。災害を契機に災害弱者に目を向けるのではなく、平時から地域で生活に困難を抱える当事者の存在、ニーズ、地域資源の理解を深め、当事者意識をもち地域福祉に関わる姿勢が減災に繋がり、有事に災害弱者へのアクセス、シームレスな支援に繋がることを実感。また平時から地域社会の構造や社会保障制度、地域に必要なニーズ・資源の把握が、被災地が復興する上で地域のレジリエンス強化を見据えた伴走支援にも繋がるのでは。

2025年7月22日(火) ~ 2026年3月31日(火)
World Bosai Forum Online 2025 -CPD Program-
参加申込み(左の赤ボタン)後、
World Bosai Forum Onlineの動画を視聴できます。
CPD申請条件をご確認の上お進みください。
試聴可能